ハクビシン(白鼻心、学名: Paguma larvata)は、アジア全域に生息する動物で、日本でも農村部や都市部で見られます。可愛らしい見た目をしていますが、以下のような危険性があります。
### 1. **農作物や家屋への被害**
– **農作物の被害**:ハクビシンは果実や野菜を好んで食べます。特にブドウや柿などの果実に被害を与えることが多く、農家にとっては大きな問題です。
– **家屋への侵入**:ハクビシンは木登りが得意で、屋根裏や天井裏に侵入することがあります。そこに巣を作り、長期間にわたって住みつくと、糞尿による汚染や悪臭が発生し、家屋の劣化を早めることがあります。
### 2. **健康へのリスク**
– **感染症の媒介**:ハクビシンはさまざまな病原体を持つ可能性があり、人間に感染するリスクがあります。
– **SARS(重症急性呼吸器症候群)**:ハクビシンは、2002年から2003年にかけてアジアで発生したSARSウイルスの中間宿主であると考えられています。
– **寄生虫**:糞尿を介して寄生虫が人間に感染することがあります。特に屋根裏や天井裏に住みつかれると、衛生的な問題が生じやすくなります。
### 3. **騒音やストレス**
– **夜行性で騒音の原因**:ハクビシンは夜行性で、夜間に活動します。家屋に侵入すると、夜間に走り回ったりする音が聞こえるため、住人にとっては不快でストレスの原因になります。
### 4. **攻撃性**
– 通常、人を襲うことはありませんが、追い詰められたり、子どもを守るために攻撃的になることがあります。噛まれると細菌感染や病気のリスクがあるため、むやみに近づかないことが重要です。
### 対策
– ハクビシンを家屋や農作物から遠ざけるためには、**屋根裏への侵入防止**(網や防護材での対策)や、農作物の周囲に防護柵を設置するなどの対策が有効です。
– ハクビシンの駆除や捕獲は、**地方自治体や専門の業者**に依頼するのが安全です。
ハクビシンは自然環境での役割も果たしていますが、人間の生活空間に侵入すると問題が発生するため、適切な対応が必要です。












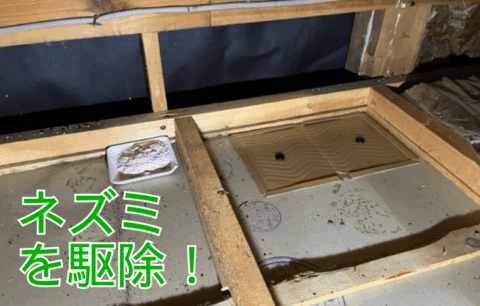



















コメント